横浜国立大学名誉教授 宮脇 昭氏緊急提言 「瓦礫でイオンの森を作ろう」
福島の被災児童のための保養センターへの募金はこちら
プロ原発推進派Svinicki氏のNuclear Regulatory Commissionへの再就任に反対署名はこちら

モントレーの南部、山奥の小さな村、ホロンの山の中に1軒ぽつんと、寂しそうに立つ小さな教会。木造の古い建物である。入口のドアも手製の古びたドアのようである。
 St. Luke's Jolon
St. Luke's Jolon
中に入ると古いアメリカ杉・レッドウッドゥの匂いが立ち込めている。壁も天井も床もレッドウッドゥ特有の古い赤茶色に包まれた寂しげな空間である。中央にある牧師の説教台も古めかしく、小さい。板を打ちつけた釘の頭が見える。元大工のフリムン徳さんには建物の材料や釘の種類まで気になる。大工をすでにやめて7年もなるのに、木造物をみる目と別嬪さんを見る目は死ぬまでやめられそうにない。後の1段上がったところのテーブルに小さな額縁に収まった写真が飾ってある。その両脇にそれぞれ3本のひまわりの花を挿した小さな瓶と3本のろうそく。壁のすき間から入ってくる風でろうそくの炎が揺れている。ただそれだけである。遺骨も遺体もない。これがフリムン徳さんの親友バブ葬式の祭壇である。
バブが9月19日に死んだ。行年82歳。妻のアルビラが死んでから丸2年になる。アルビラに呼ばれたのだろうか。死人は3年以内に誰かを呼ぶと日本で聞いたことがある。バブはアルビラの死後、娘の住むモンターナ州に家を買い、娘夫婦の世話になっていた。葬式は友人の多いカリフォルニア・ラックウッドゥに戻って、生前メンバーであったこの教会でやることになった。モンターナからは車で2日間の行程である。
幅20センチ、高さ30センチほどの額縁にはバブが立った全身のカラー写真が入っている。顔写真ではない。話しかけてくるような迫力はない。着古しのジーパン、突き出た膝の部分が白く変色している。そのジーパンを肩からの吊りバンドが吊っている。ねずみ色のチェックの半そでシャツから痩せたバブの腕が枯れ木のように垂れている。背景は4、5本のひまわりである。バブの背丈の2倍以上はある。モンターナの彼の裏庭で育てたものだろう。写真は庭仕事中のスナップショットのようだ。これがバブの葬式用の写真である。
ネクタイ姿の写真を重んじる日本、普段着のままで良いアメリカの田舎、どうしてこうも日本人とアメリカの田舎は違うのだろうか。日本人のフリムン徳さんの感覚からすれば、葬式用の写真はバブが元気で輝いていた頃のキチンとした背広にネクタイ姿の大きな顔写真がふさわしい。でも長年こんな山の中で暮らしていたバブのネクタイ姿の写真が探せなかったと思った。わかる気がする。この辺の村で、ネクタイ姿を見たのを思い出すのは難しい。フリムン徳さんもここに住んで15年になるけど、ネクタイ、背広姿をしたことがない。ブドウ畑と牧場に囲まれた本当のアメリカの田舎ではジーパンが一番似合う。
フリムン徳さんもネクタイ姿の写真がなくて困ったことがある。
「あなたの出版した本の書評を載せますので、写真を送ってください」と、私が本を出版した時に、日本の大きな新聞社から連絡が来た。大きな新聞社に元大工のフリムン徳さんの書いた本書評が載るはずがない。当たり前のことである。このあたり前のことが当たり前でないことに成る時もあるから世の中おもろい。フリムン徳さんの日本の同級生の友達が、その大きな新聞社の記者だったから、頼み込んだのである。Tシャツ姿の写真を送ったら、「ネクタイ姿の写真を送ってください」と再連絡があった。古いアルバムを引っ張り出して、何十年か前の日本で撮ったネクタイ姿の写真を送った覚えがある。日本は本を出版する人はネクタイをする人と決めているような気がして、おかしかった。バブの晩年の庭仕事中のスナップショットは貧弱で、裏庭に立った案山子のようで、寂しかった。翌年死んだ89歳になる友達のジムの葬式の写真も、半袖シャツに、着古しのジーパンと吊りバンド姿だった。普段着のままの葬式用の写真はバブだけではなかった。バブの葬式の写真の横の瓶に生けてあるひまわりと写真の背景の大きなひまわりを見て、バブはひまわりが好きだったことをフリムン徳さんは思い出し、懐かしさが静かに胸に込み上げてきた。娘のティーナの気配りに心を打たれた。
葬式は午前11時に始まった。バブの娘ティーナ夫婦、フリムン徳さんと嫁はんは、準備のため9時に教会に着いた。ティーナが一番初めにしたことは、ひまわりの花を小さな花瓶に挿し、それを外に出して太陽に当てることだった。お日様に向って咲くひまわりの花にはお日様に当てて、元気なひまわりをバブに供えたかったのだろう。
教会の中は真ん中の通路の両脇に長椅子が並ぶ。最前列に5人ずつ、その後の列に5人ずつ、20人ほどがバブの親族である。その中のたった二人の日本人、フリムン徳さんと嫁はんは親族のうちである。見渡してみると、出席者のほとんどが白人。黒人さんは一人もいない。4、5人のメキシカンがいる。でも、女性のメキシカンも白人女性と区別がつかない。きっと、日本女性のように、流行の髪の色を赤色に染めているのだろう。元大工のフリムン徳さんは材木だけをよく観察していると思ったら、おなごはんの髪の毛の色まで観察している。助平―なやっちゃ。50人収容のこの小さな教会の真ん中の通路に20ほどの椅子が追加され、小さな教会は満員状態である。
葬式が始まってもフリムン徳さんにはどうも葬式の雰囲気が感じられない。いつもより人数が多い普通のミサのような気がする。
黒の喪服の人は親族の5、6人だけ。他の人ほとんどが、ジーパンにTシャツの普段着のままである。ネクタイをした男はアラスカから来た息子のグレン一人だけ。フリムン徳さんと嫁はんも普段着である。サンフランシスコや、ロスアンジェルスの都会の葬式では、黒の喪服、ネクタイをした人が多いが、ここラックウッドゥの田舎では普段着が普通である。
違うのは参列者の服装だけではなかった。
キリスト教の葬式の儀式が終わると、バブの友人達が代わる代わる説教台に立ち、バブの小さい頃からの人生歴史を面白おかしく話して、みんなを笑わせる。ほとんどがバブの失敗談である。大笑いの連続であった。娘のティーナは笑っては泣き、泣いては笑うのに忙しかった。その度に旦那のスティーブも彼女の肩を抱きしめるのに忙しかった。まるで、落語か、漫才を聞いているみたいだった。
葬式が終わった後のパーティーも普段のごく普通のパーティーだった。
礼拝堂の隣の建物にある小さなキッチンには、バブが好きだった大きなソーセージを挟んだパン、野菜サラダ、ビーンズ、パイなどが盛られている。それをおのおの使い捨ての紙皿に取り、缶入りのコーラやオレンジジュースを選ぶ。屋外に並べられたテーブルで思い思いの席に座って食べる。参加者全員が車を運転してきているので、アルコールは一切なしである。アルコール好きのフリムン徳さんにも不満はない。喪主のティーナが準備したのは飲み物とサンドイッチのパン、ソーセージだけ。野菜サラダ、デザートのパイは何人かの持ち寄りである。なんと金のかからない、簡単で質素なアメリカの田舎の葬式かと、心に残る。葬式の費用で頭を悩ます日本人に見せたい。
もちろん、香典を包む習慣もない。
以前、日本人の習慣の抜け切れないフリムン徳さんは、二度ほど、知り合いの白人が死んだ時、10ドルの香典を包んで供えた。しばらくしてから、一つの家族からは「このお金は教会に寄付します」と、もう一つの家族からは「このお金で記念に死んだ彼の好きなカエデを植えます。紅葉したら見にきてください」と返礼の手紙が来た。
どうしてこうも日本の葬式と違うのだろう。
アメリカの田舎の人は普段着のままで、普段着のままの人を葬式してあの世へ送る。それに比べると日本の葬式は豪華絢爛である。黒の喪服にネクタイ、真珠の首飾り、数え切れないほどの豪華な花輪、おいしいご馳走に囲まれてあの世へ行く。数年前、嫁はんは母親の葬式に喜界島へ行った。その時の葬式の様子を聞くと、喜界島の葬式とアメリカの田舎ブラッドレーの葬式は、大金持ちと超貧乏人の葬式の違いがあるようだ。
人間は死んだら、ただの灰か ?
バブが生きていた時に聞いたことがある。
「人間は死んだら、ただの灰になり、それで終わりだ」と言う。その灰も、
「郵便小包で送ってくれるよ」と言う。バブとアルビラの夫婦は、死んだら、焼いて灰にして郵便小包で送ってくれる会社と契約をしていた。一人約2400ドル(19万2千円)で、アメリカのどこで死んでも焼いて灰にして、箱に入れて郵便小包で送ってくれる。
アルビラが死んで、しばらくして、バブと二人で、郵便局へアルビラの灰の小包を受け取りに行った。バブは、アルビラの灰の入った箱を無造作に車の後のトランクに入れようとするではないか。
「バブ、ちょっと、待ってくれ」
とフリムン徳さんはバブからその箱を取り上げて、丁重に膝に乗せた。
「日本では丁重に抱いて持ち運び、花、線香、ろうそく、酒を供えて、拝むのですよ」
と言うと、「死んだら、灰と同じ、生きていた時の思い出だけが大事」
とそっけない。アルビラは白人の中で、フリムン徳さん夫婦に最も親切だった。フリムン徳さんは感謝の気持ちでアルビラの箱を撫でながら眺めた。ふと箱の底に目が行った。メイドインチャイナ。中国はアメリカ人の灰箱まで作っている。そのうち、中国はアメリカ人の子供までつくるかもしれない。
アルビラは、生きていた時、「教会の裏の墓地に埋めてくれ」
と言っていたのにと言うと、バブは、「死んだら、もう関係ない」と自分の行くモンターナに持って行った。バブだけではないようだ。フリムン徳さんがシアトルの山の中に住んでいた頃、近所の白人のおじさんはもっと変わったことをしていた。
ある日の夕方、うちで二人ビールを飲んでいた時、自分の車の後のトランクを開けて見せてくれた。30センチ真四角ほどの木の箱である。
「これは、私の妻。埋める墓地を買ってないのと、預ける金がもったいないから、自分が死ぬまで、こうして車のトランクに入れて持ち歩く」
先祖代々のウヤフジ(ご先祖)を大事にする日本、死んだら、終わりだと考えるアメリカ人の違いは大きい。「死んだウヤフジを拝まないで何を拝むのか」と聞くと、キリスト様を拝むのだという。フリムン徳さんは死んだごウヤフジに、「エッセーの達人にしてくれ」と毎晩拝んでいる。葬式の違い、死んだ人への思いの違いは宗教の違いによるようだ。
フリムン徳さんの葬式は明るく、楽しくやろう!!
幼い頃をゆかいに過ごした、懐かしい喜界島の同級生に囲まれて、普段着のままで、島踊り、島唄、朝花、どんどんしぇー、徳之島ツッキャリ節、六調で、口笛を吹きドンちゃん騒ぎをして欲しい。フリムン徳さんは、晩酌を減らして、葬式のドンちゃん騒ぎの費用に金を貯め始めようと思っている。でも、みんなの足腰が元気なうちに、フリムン徳さんも元気なうちに、葬式をやりたい。 2011

by フリムン徳さん
プリムン徳さんはエッセイ本「フリムン徳さんの波瀾万丈記」 を出版されています。
を出版されています。

フリムン徳さ〜ん!! 私もお葬式に行きますよ〜〜〜。 私が早かったらフリムン徳さんも来てくださいね! そして楽しくやりましょう〜〜。

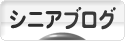
福島の被災児童のための保養センターへの募金はこちら
プロ原発推進派Svinicki氏のNuclear Regulatory Commissionへの再就任に反対署名はこちら
モントレーの南部、山奥の小さな村、ホロンの山の中に1軒ぽつんと、寂しそうに立つ小さな教会。木造の古い建物である。入口のドアも手製の古びたドアのようである。
 St. Luke's Jolon
St. Luke's Jolon中に入ると古いアメリカ杉・レッドウッドゥの匂いが立ち込めている。壁も天井も床もレッドウッドゥ特有の古い赤茶色に包まれた寂しげな空間である。中央にある牧師の説教台も古めかしく、小さい。板を打ちつけた釘の頭が見える。元大工のフリムン徳さんには建物の材料や釘の種類まで気になる。大工をすでにやめて7年もなるのに、木造物をみる目と別嬪さんを見る目は死ぬまでやめられそうにない。後の1段上がったところのテーブルに小さな額縁に収まった写真が飾ってある。その両脇にそれぞれ3本のひまわりの花を挿した小さな瓶と3本のろうそく。壁のすき間から入ってくる風でろうそくの炎が揺れている。ただそれだけである。遺骨も遺体もない。これがフリムン徳さんの親友バブ葬式の祭壇である。
バブが9月19日に死んだ。行年82歳。妻のアルビラが死んでから丸2年になる。アルビラに呼ばれたのだろうか。死人は3年以内に誰かを呼ぶと日本で聞いたことがある。バブはアルビラの死後、娘の住むモンターナ州に家を買い、娘夫婦の世話になっていた。葬式は友人の多いカリフォルニア・ラックウッドゥに戻って、生前メンバーであったこの教会でやることになった。モンターナからは車で2日間の行程である。
幅20センチ、高さ30センチほどの額縁にはバブが立った全身のカラー写真が入っている。顔写真ではない。話しかけてくるような迫力はない。着古しのジーパン、突き出た膝の部分が白く変色している。そのジーパンを肩からの吊りバンドが吊っている。ねずみ色のチェックの半そでシャツから痩せたバブの腕が枯れ木のように垂れている。背景は4、5本のひまわりである。バブの背丈の2倍以上はある。モンターナの彼の裏庭で育てたものだろう。写真は庭仕事中のスナップショットのようだ。これがバブの葬式用の写真である。
ネクタイ姿の写真を重んじる日本、普段着のままで良いアメリカの田舎、どうしてこうも日本人とアメリカの田舎は違うのだろうか。日本人のフリムン徳さんの感覚からすれば、葬式用の写真はバブが元気で輝いていた頃のキチンとした背広にネクタイ姿の大きな顔写真がふさわしい。でも長年こんな山の中で暮らしていたバブのネクタイ姿の写真が探せなかったと思った。わかる気がする。この辺の村で、ネクタイ姿を見たのを思い出すのは難しい。フリムン徳さんもここに住んで15年になるけど、ネクタイ、背広姿をしたことがない。ブドウ畑と牧場に囲まれた本当のアメリカの田舎ではジーパンが一番似合う。
フリムン徳さんもネクタイ姿の写真がなくて困ったことがある。
「あなたの出版した本の書評を載せますので、写真を送ってください」と、私が本を出版した時に、日本の大きな新聞社から連絡が来た。大きな新聞社に元大工のフリムン徳さんの書いた本書評が載るはずがない。当たり前のことである。このあたり前のことが当たり前でないことに成る時もあるから世の中おもろい。フリムン徳さんの日本の同級生の友達が、その大きな新聞社の記者だったから、頼み込んだのである。Tシャツ姿の写真を送ったら、「ネクタイ姿の写真を送ってください」と再連絡があった。古いアルバムを引っ張り出して、何十年か前の日本で撮ったネクタイ姿の写真を送った覚えがある。日本は本を出版する人はネクタイをする人と決めているような気がして、おかしかった。バブの晩年の庭仕事中のスナップショットは貧弱で、裏庭に立った案山子のようで、寂しかった。翌年死んだ89歳になる友達のジムの葬式の写真も、半袖シャツに、着古しのジーパンと吊りバンド姿だった。普段着のままの葬式用の写真はバブだけではなかった。バブの葬式の写真の横の瓶に生けてあるひまわりと写真の背景の大きなひまわりを見て、バブはひまわりが好きだったことをフリムン徳さんは思い出し、懐かしさが静かに胸に込み上げてきた。娘のティーナの気配りに心を打たれた。
葬式は午前11時に始まった。バブの娘ティーナ夫婦、フリムン徳さんと嫁はんは、準備のため9時に教会に着いた。ティーナが一番初めにしたことは、ひまわりの花を小さな花瓶に挿し、それを外に出して太陽に当てることだった。お日様に向って咲くひまわりの花にはお日様に当てて、元気なひまわりをバブに供えたかったのだろう。
教会の中は真ん中の通路の両脇に長椅子が並ぶ。最前列に5人ずつ、その後の列に5人ずつ、20人ほどがバブの親族である。その中のたった二人の日本人、フリムン徳さんと嫁はんは親族のうちである。見渡してみると、出席者のほとんどが白人。黒人さんは一人もいない。4、5人のメキシカンがいる。でも、女性のメキシカンも白人女性と区別がつかない。きっと、日本女性のように、流行の髪の色を赤色に染めているのだろう。元大工のフリムン徳さんは材木だけをよく観察していると思ったら、おなごはんの髪の毛の色まで観察している。助平―なやっちゃ。50人収容のこの小さな教会の真ん中の通路に20ほどの椅子が追加され、小さな教会は満員状態である。
葬式が始まってもフリムン徳さんにはどうも葬式の雰囲気が感じられない。いつもより人数が多い普通のミサのような気がする。
黒の喪服の人は親族の5、6人だけ。他の人ほとんどが、ジーパンにTシャツの普段着のままである。ネクタイをした男はアラスカから来た息子のグレン一人だけ。フリムン徳さんと嫁はんも普段着である。サンフランシスコや、ロスアンジェルスの都会の葬式では、黒の喪服、ネクタイをした人が多いが、ここラックウッドゥの田舎では普段着が普通である。
違うのは参列者の服装だけではなかった。
キリスト教の葬式の儀式が終わると、バブの友人達が代わる代わる説教台に立ち、バブの小さい頃からの人生歴史を面白おかしく話して、みんなを笑わせる。ほとんどがバブの失敗談である。大笑いの連続であった。娘のティーナは笑っては泣き、泣いては笑うのに忙しかった。その度に旦那のスティーブも彼女の肩を抱きしめるのに忙しかった。まるで、落語か、漫才を聞いているみたいだった。
葬式が終わった後のパーティーも普段のごく普通のパーティーだった。
礼拝堂の隣の建物にある小さなキッチンには、バブが好きだった大きなソーセージを挟んだパン、野菜サラダ、ビーンズ、パイなどが盛られている。それをおのおの使い捨ての紙皿に取り、缶入りのコーラやオレンジジュースを選ぶ。屋外に並べられたテーブルで思い思いの席に座って食べる。参加者全員が車を運転してきているので、アルコールは一切なしである。アルコール好きのフリムン徳さんにも不満はない。喪主のティーナが準備したのは飲み物とサンドイッチのパン、ソーセージだけ。野菜サラダ、デザートのパイは何人かの持ち寄りである。なんと金のかからない、簡単で質素なアメリカの田舎の葬式かと、心に残る。葬式の費用で頭を悩ます日本人に見せたい。
もちろん、香典を包む習慣もない。
以前、日本人の習慣の抜け切れないフリムン徳さんは、二度ほど、知り合いの白人が死んだ時、10ドルの香典を包んで供えた。しばらくしてから、一つの家族からは「このお金は教会に寄付します」と、もう一つの家族からは「このお金で記念に死んだ彼の好きなカエデを植えます。紅葉したら見にきてください」と返礼の手紙が来た。
どうしてこうも日本の葬式と違うのだろう。
アメリカの田舎の人は普段着のままで、普段着のままの人を葬式してあの世へ送る。それに比べると日本の葬式は豪華絢爛である。黒の喪服にネクタイ、真珠の首飾り、数え切れないほどの豪華な花輪、おいしいご馳走に囲まれてあの世へ行く。数年前、嫁はんは母親の葬式に喜界島へ行った。その時の葬式の様子を聞くと、喜界島の葬式とアメリカの田舎ブラッドレーの葬式は、大金持ちと超貧乏人の葬式の違いがあるようだ。
人間は死んだら、ただの灰か ?
バブが生きていた時に聞いたことがある。
「人間は死んだら、ただの灰になり、それで終わりだ」と言う。その灰も、
「郵便小包で送ってくれるよ」と言う。バブとアルビラの夫婦は、死んだら、焼いて灰にして郵便小包で送ってくれる会社と契約をしていた。一人約2400ドル(19万2千円)で、アメリカのどこで死んでも焼いて灰にして、箱に入れて郵便小包で送ってくれる。
アルビラが死んで、しばらくして、バブと二人で、郵便局へアルビラの灰の小包を受け取りに行った。バブは、アルビラの灰の入った箱を無造作に車の後のトランクに入れようとするではないか。
「バブ、ちょっと、待ってくれ」
とフリムン徳さんはバブからその箱を取り上げて、丁重に膝に乗せた。
「日本では丁重に抱いて持ち運び、花、線香、ろうそく、酒を供えて、拝むのですよ」
と言うと、「死んだら、灰と同じ、生きていた時の思い出だけが大事」
とそっけない。アルビラは白人の中で、フリムン徳さん夫婦に最も親切だった。フリムン徳さんは感謝の気持ちでアルビラの箱を撫でながら眺めた。ふと箱の底に目が行った。メイドインチャイナ。中国はアメリカ人の灰箱まで作っている。そのうち、中国はアメリカ人の子供までつくるかもしれない。
アルビラは、生きていた時、「教会の裏の墓地に埋めてくれ」
と言っていたのにと言うと、バブは、「死んだら、もう関係ない」と自分の行くモンターナに持って行った。バブだけではないようだ。フリムン徳さんがシアトルの山の中に住んでいた頃、近所の白人のおじさんはもっと変わったことをしていた。
ある日の夕方、うちで二人ビールを飲んでいた時、自分の車の後のトランクを開けて見せてくれた。30センチ真四角ほどの木の箱である。
「これは、私の妻。埋める墓地を買ってないのと、預ける金がもったいないから、自分が死ぬまで、こうして車のトランクに入れて持ち歩く」
先祖代々のウヤフジ(ご先祖)を大事にする日本、死んだら、終わりだと考えるアメリカ人の違いは大きい。「死んだウヤフジを拝まないで何を拝むのか」と聞くと、キリスト様を拝むのだという。フリムン徳さんは死んだごウヤフジに、「エッセーの達人にしてくれ」と毎晩拝んでいる。葬式の違い、死んだ人への思いの違いは宗教の違いによるようだ。
フリムン徳さんの葬式は明るく、楽しくやろう!!
幼い頃をゆかいに過ごした、懐かしい喜界島の同級生に囲まれて、普段着のままで、島踊り、島唄、朝花、どんどんしぇー、徳之島ツッキャリ節、六調で、口笛を吹きドンちゃん騒ぎをして欲しい。フリムン徳さんは、晩酌を減らして、葬式のドンちゃん騒ぎの費用に金を貯め始めようと思っている。でも、みんなの足腰が元気なうちに、フリムン徳さんも元気なうちに、葬式をやりたい。 2011

by フリムン徳さん
プリムン徳さんはエッセイ本「フリムン徳さんの波瀾万丈記」

フリムン徳さ〜ん!! 私もお葬式に行きますよ〜〜〜。 私が早かったらフリムン徳さんも来てくださいね! そして楽しくやりましょう〜〜。
























コメント
コメント一覧 (15)
私の友達もご主人を20年前に亡くされましたが、未だに、お墓を買うお金もなく、お家に骨箱がありますよ。
田舎だと安いんでしょうが、残されたものが御墓参りできる範囲だとすっごく高いです。
日本は、土地がないので、お寺さんが永代供養を進めます。(お墓を買うお金を持ってられる方は、別ですよ)
私も、亡くなったら賑やかに精進落としをしてくれたらいいと思います(笑)
日本のような、お通夜とかお葬式はないのですか?さっぱりしていていいですね。また、こんなふうに明るい感じで送ってもらえるといいですね。
今日本では葬式の値段が安くなり、簡素化されています。
20年前に祖父が亡くなった時は父親が会社経営ではぶりもよかったので盛大にやりました。
私の結婚式の時もお酒飲み放題で無礼講でした。
父も会社をダメにし、私も出戻ったので果たしてどうなるやら。
父は葬式はいらないと言っていました。
フリムン徳さんの記事を拝見して思い出しました。
幼少期をアメリカで過ごした主人は「死んだ人の体は魂のないただの物だ」と言うのです。
少し考え方が変わっているとは思っていましたが、これにはお墓参りが当たり前の私も驚いてしまいました。
やはりアメリカではそういった方が多いのですね。
記事を読んで納得しました。
この方は何と日本人的な人だろうと思っていました。
徳さん、多くの場合笑いのエピソードでお葬式をされ、死んだら「無」である事がアメリカでは普通の様ですね。
日本人は形式を重んじお葬式も大きくするのが美徳の様に思われていますが形式にとらわれないお葬式のほうが良い様な気がしますね。
志しを忘れないようにしていきたいな‥と思っています。
葬式は亡くなる前でも、亡くなってからでも、楽しくドンちゃん騒ぎがいいですねえ。
フリムン徳さん
アメリカのこの山の中で、何人かの葬式に行きましたが、
お通夜はないみたいです。
葬式は死んでから、3、4日後に、やるようです。
土曜日か日曜日が多いようです。
フリムン徳さん
葬式はお金がかからない方がいいですよねえ。
フリムン徳さん
私は人間は死んでもあの世で生きて、子孫を見守ってくれていると思います。
アメリカは死んだら、終わりみたいですねえ。
フリムン徳さん
葬式は型式にとらわれないで、楽しく、ドンちゃん騒ぎがいいですよね。
フリムン徳さん
アメリカの田舎は葬式にお金がかからないから、香典が要らないと思います。
フリムン徳さん
夫は 5年前に、 両親と同じメモリアルサービスの会社に事前に契約をしてあります。 墓碑も両親と同じ石屋さんで作ってもらいました。
実際に 自分の葬儀をどのように するのかは、事前に考えておくと いいのでしょうが・・・人間は生きてきたように 最後を迎えるのでしょうか。
元気なうちに 親しい人々と 食事をする機会をもっておきたいなぁと、ふと 思います。係累がいないのですが、 まだ 体が動くうちでしたら、お付き合いのあった人々と触れ合うことができると思いますね。
夫は 家の中で 一人ではなく 声がするのは、幸せだと 話しています。
胸の真ん中に染み込む名文やと思います。
「夫は 家の中で 一人ではなく 声がするのは、幸せだと 話しています」
フリムン徳さん